岡山県立真庭高等学校
竹内成長 / 真庭高等学校校長 ・ 甲本乃之 / 経営ビジネス科教諭

実践する「経営ビジネス科」が描く、新しい高校教育のカタチ
- 高校生たちが、大人と打ち合わせをしている。
高校生たちが、学校の外でプロジェクトを動かしている。
岡山県立真庭高等学校の「経営ビジネス科」
高校生たちが学校を出て、地域の店舗にいる。地元企業にいる。地域の現場にいる。そこにあるのは「ビジネスの現場」。高校生たちは社会のなかで「実践」を学んでいる。
令和3年度から文部科学省の「マイスター・ハイスクール事業」の指定を受け、経営ビジネス科・食農生産科を新設した真庭高校。
そのなかで、「経営ビジネス科」はなぜ、従来の商業科教育の枠を超えた「実践的なビジネス教育」が可能になったのか。そして、生徒たちはどのように成長していったのか。
「Team Maniwa」を合い言葉に、生徒・教職員・地域が1つのチームとなって取り組む真庭高校「経営ビジネス科」について、竹内成長校長と、甲本乃之先生に取材させていただいた。 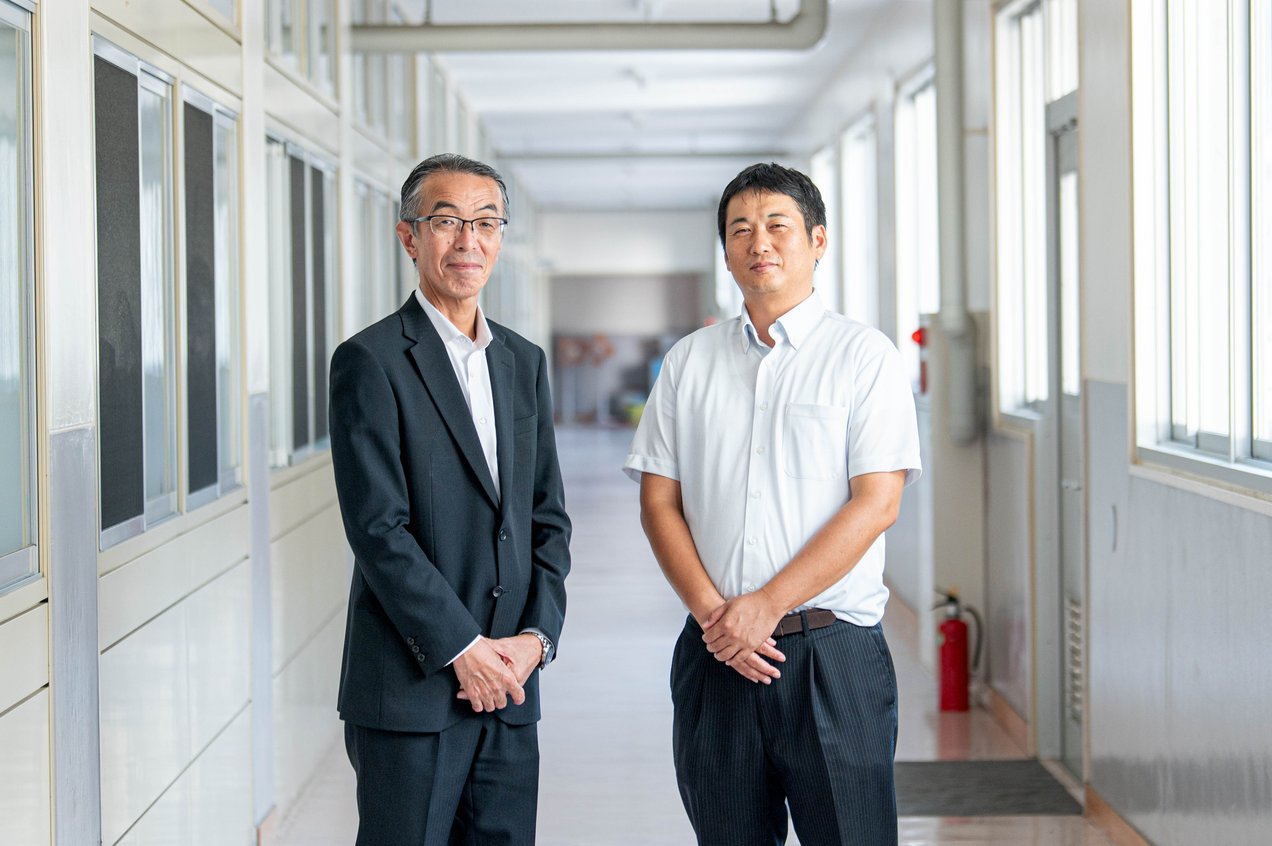
- 真庭高校の「経営ビジネス科」の特徴について教えてください。
- 竹内校長:
そうですね。一般的な「商業科」の授業とは異なり、実践的な「商品開発」や「流通」「マーケティング」といった実社会に即した分野に、しっかりと授業の時間を取っています。
また、地域の方や、真庭市を通じてマーケティングやコミュニケーションの専門家にも積極的に入っていただき、学校の内外でいろんな経験ができるようになっています。「経営ビジネス」の名前のとおり、(企画で終わらない、実際カタチにする)商品開発であったり、アプリ開発であったり。また、人前で話す機会も多いと思います。
甲本先生:
真庭高校の「経営ビジネス科」では、「資格の縛り」が少ないんです。他学校さんの商業科はどちらかと言えば、「資格取得」に重きを置いているんですが、うちは資格を取るための授業はしていません。
そうではなくて、実際に「商品開発」や「マーケティング」を実践するなかで、生徒自身が「やっぱり資格を取っておいたほうが良いな」と気づいてから、資格の勉強を始めるという流れになっていて、生徒が「自覚的な勉強」をしています。私は商業高校出身ですけど、真庭高校みたいな授業だったら良かったのになと思います(笑)。
竹内校長:
ですので、「学ぶ面白さ」が感じられると言いますか。たとえばアプリ開発だったら、ゲーム好きな生徒がちょっとやってみて、それがカタチになったら面白くなって。どんどん前向きに、前のめりになっていくんです。
生徒たちのそういう様子を見ていると、机上の空論で終わらない、頭でっかちではない、学んでいることがちゃんと将来に結びついていることを感じます。 
- 具体的にはどのような授業を行っているのでしょうか?
- 甲本先生:
2年次では「商品開発」という授業があり、たとえば今はもうつくられなくなった地元のコッペパンを復活させるプロジェクトを生徒と地元企業が立ちあげ、ワンアイデア足して「ひるぜん焼そば」と真庭産の野菜を使った「特製焼きそばパン」をつくり、販売していく。
やってみると、企業さんも本気で関わってくださるので、こちらもしっかりと時間をかけて、本気で応えていく。そういう授業になっています。
また、真庭観光局から出している「MBM(真庭バイオマスマイスター)」の資格を取得する授業もあります。観光局の方や市役所の方からのレクチャーを受けて、資格を取得すれば、視察団体が訪れる「バイオマスツアー」に、ガイドとして案内をすることができます。
竹内校長:
今回であれば、岡山県南の高校生に向けて、「MBM」の資格を取得した「経営ビジネス科」の生徒がガイドを担当しました。いやあ、もうびっくりですよね。生徒たちが前に出て、しっかりとバイオマスについて説明していく。
ただ資格を取るだけではなく、ちゃんと「生かす場」が用意されています。最近では関西のほうから「MBMの資格を取っている生徒さんに案内いただけませんか?」という依頼が来るほどになっています。
1年次には「起業家育成」の講義もあります。東京の大学で実際に起業された方を講師として招いて、ビジネスアイデアや新しいアイデアを生み出す「考え方(起業家精神)」を学んでいます。 
- アイデアが生かせる「実践の場」があるというのは良いですね。
- 甲本先生:
先も少しお話させていただきましたが、授業の一環で「アプリ開発」も進めています。それは同志社大学の学生さんたちと連携しながら、「学校生活」のなかで使える実用的なアプリや、地域の方々も関われるようなSNSのコミュニティ機能を持ったアプリなど、「使えるアプリ」をつくる授業になっています。
竹内校長:
空き店舗を活用したカフェ「machie(マチエ)」の運営もしています。もともと蕎麦屋だった空き店舗をお借りして改修し、経営ビジネス科の教員が「営業許可」の資格も取得。毎週金曜日、生徒たちが中心となって自分たちなりのメニューを販売しています。
店舗の運営だけではなく、そのお店のホームページをつくるためにWEB系やデザイン系の講座も用意しています。ひとつのプロジェクトであっても、さまざまなキリクチから多くの実践的な学びが得られるような工夫をしています。
生徒たちの「やってみたい」ができる授業構成になっていると思います。 
- 「実践の場」で有名なのが、全国優勝を果たした「竹パウダー」ですよね。
- 甲本先生:
そうですね。「R6全国高校生ビジネスアイデアコンテスト」で「文部科学大臣賞」「最優秀賞」を受賞。「岡山ガスビジネスプランコンテスト2024」でも「グランプリ」を受賞しました。
「近所の放置竹林を何とかしたい」や「草取りに苦労する父の役に立ちたい」と思う生徒たちのアイデアから「なくす竹害~竹と液肥でイノベーション~」と題したビジネスプランが生まれました。 - 真庭高校経営ビジネス科の3年生の活躍
- 甲本先生:
アイデアをカタチにしていく過程で、さまざまな市内の企業さんや地域の方と協働しながらどんどんブラッシュアップされて。生徒たちも「このプランはちゃんと社会的に意義のあることなんだ」と気づいていけたのも大きかったと思います。
ただ、スイスイと受賞できたわけではなくて2年生の春の別のコンテストでは、万全を期して5ヶ月をかけて出場したのに、箸にも棒にも掛からなかったんです。でも生徒たちはそこであきらめず、3年生に持ち越して、よりプランの精度を高めていった。その姿勢には驚かされました。 
- 「実践の場」に地域の方や企業の方、行政の方など、多くの方々が関わっているように感じます。
- 竹内校長:
令和3年に「マイスター・ハイスクール」の指定を受けたのが転換だったと思います。専門性の高い特色を持たせようと「経営ビジネス科」「食農生産科」「看護科(看護科は以前から存在)」となり、それぞれどのような「科」にするか、学校内外の方、地域の方、真庭市の職員、コーディネーターなど、多くの方が携わって議論を交わしました。
その議論があったからこそ、学校・地域・行政の距離がグッと縮まり、コミュニケーションを取ったり、サポートし合ったりの体制が整い、できることがたくさん増えたんだと思います。
いくつもの高校を抱える自治体の場合、特定の学校にチカラを入れることはできません。しかし真庭市では、庁内の複数の部署が連携し、いろんな角度から支えてくださっているので、生徒たちの「実践の場」がたくさん用意されています。
甲本先生:
おかげで、生徒自身のチカラがつきますよね。生徒たちが企画運営するプロジェクトがそのまま実社会にコミットしているので、地域の方や企業の方からも「本気の」と言いますか、「お客様ではない、いち関係者としてのアドバイス」がもらえます。
「これは良かった」「ここはまだまだなんじゃないか」「こう改善すれば良いんじゃないか」など、実社会の会議と変わらない意見が飛びます。生徒たちも「社会に対してのプロジェクトを動かしている」という自覚が芽生えています。 
- こういう授業を通して、どのようなチカラをつけてほしいというのはありますか?
- 竹内校長:
「チームをつくるチカラ」ですね。就職するにせよ、起業するにせよ、ひとりで生きていくということはほとんどありません。「まったくない」と言っても良いほどです。
チームがつくれるかどうか。チームのなかでどう振る舞えるか。「リーダー」として「フォロワー」として、そのチームをどう引っ張っていくか。社会のなかではそういうチカラが必要になると考えているので、プロジェクトを通して「チームをつくるチカラ」を意識しています。
たとえば、プロジェクトのなかでうまくいかないこと、失敗することって多々あります。でもそこから立ち上がって、チームを鼓舞しながら、できることを考えて、ひとりではなくチームとしてまた前に進めていく。
思いどおりにいかないことがあっても、自分を変革しながらリーダーシップを発揮していく。そういうことのできる生徒になってもらうカリキュラムをつくっています。
そういう思いもあって、いま真庭高校では「Team Maniwa」を掲げ、「チーム」を意識するようにしています。学校はひとつのチームです。経営ビジネス科・食農生産科・看護科と「科」はバラバラでも、協働して「ひとつのチーム」として動いていく。
そうすることで、以前よりも「俯瞰的(ふかんてき)にものごとを捉えて、チームのなかで自分を生かしていく」生徒が増えたように思います。 
- 甲本先生:
こういう高校はほかにないと思います。地域と真庭高校に「繋がり」が確かにあって、「真庭市」からも「地域」からも後押しがある。「なにかをつくっていく」にとても適した学校だと思います。
見ていただければ、良さがすぐにわかります。生徒たちの表情、取り組む姿勢。まわりの大人たちの本気度や、真庭市との連携。ぜひ一度、真庭高校へ見学に来られてください。きっとビックリされると思います。
竹内校長:
いつでもお待ちしています。 
- 「経営ビジネス科」でしかできない「学び」。
それは「受け身」ではない、「実践する場」がいくつもあるということ。
実践を通して、知識も、経験も、心も成長していく。
そして実践の場は、地域にある。
地域に出て、地域の魅力や課題にコミットする「探究的学び」により、地域の未来を自分の将来に重ねることができる。
まさに、「マイスター・ハイスクール事業」で目指してきたことだと思う。
何より印象的だったのは、生徒たちの姿だった。
うまくいかなくても「もう一度やってみよう」と挑戦する姿。地元の大人たちと話しながらプロジェクトを進めていく姿。何かに熱中する姿。自分の意見をまとめて伝える姿……。
生徒ひとりひとりが、とても大きく見えた。
「真庭には、真庭高校経営ビジネス科がある」という強みを感じた。







